みらい育成アワード
2025Award 2025
2025年9月20日、JPタワーホール(東京都千代田区)にて「みらい育成アワード2025~知見、実践、その想いを分かち合う~」を開催しました。本アワードは、2024年度に採択した財団の助成先の皆さまの中から、優れた活動・成果に賞をお贈りするとともに、培われたナレッジやノウハウ、その想いを分かち合うことを目的としており、当日は132名の方にご参加いただきました。
冒頭、理事長の宮永俊一が開会の挨拶に立ち、まずは成功裏に終わった「高校生MIRAI万博」への謝辞を述べました。続けて、先行き不透明な社会における教育の重要性を強調し、「この場での活発な意見交換や交流を通じて、皆さん一人ひとりが未来への新たな気づきや繋がりを持ち帰っていただきたいと思います」と参加者の皆さまに呼びかけました。また、昨年に引き続き文部科学省 初等中等教育局 参事官(高等学校担当)橋田 裕様にご来場いただき、壇上にてご挨拶いただきました。
続いて行われた授賞式では、財団の選考委員による審査を経て選ばれた各カテゴリーのグランプリ、準グランプリ、三菱みらい育成財団賞※を受賞した10団体の皆さまに記念品と目録を贈呈しました。
授賞式後には、グランプリ受賞団体の皆さまによる取組み事例のプレゼンテーションが行われました。各プレゼンテーションの後には、周囲の参加者同士で感想を共有するグループディスカッションが行われ、その後、プレゼンターに対して、参加者から具体的な質問を投げかける全体での質疑応答が実施されました。「参考にしたい」「詳細を知りたい」といった意見や、「どのような苦労があったのか」といった質問が寄せられ、受賞者への賞賛とともに意見交換が行われました。
その後、「探究的な学びの充実に向けて~つながる・深める・拡げる~」をテーマに、採択先の4団体によるパネルディスカッションが行われました。最後に実施された振り返りワークショップでは、参加者が少人数のグループで意見を共有し、グループ替えをしながら、それまでの内容で印象に残ったことやその理由について多様な視点からディスカッションが行われました。
※ 対象団体が5~9団体のカテゴリーはグランプリのみ授与。対象団体が4団体以下のカテゴリーは「三菱みらい育成財団賞」を授与
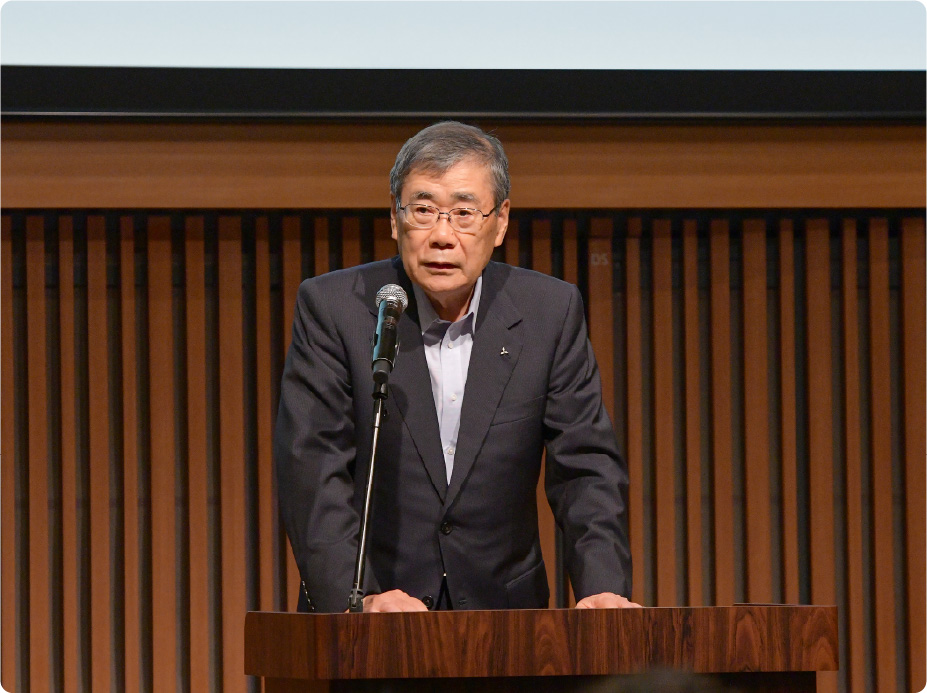
宮永理事長が開会の挨拶を行い、教育の重要性と本アワードの意義について
語りました

2025年度アワードの受賞者の皆さま
受賞結果
グランプリ
| カテゴリー1(東地区) | 群馬県立伊勢崎高等学校 |
|---|---|
| カテゴリー1(西地区) | 京都市立京都奏和高等学校 |
| カテゴリー2 | 株式会社 トモノカイ |
| カテゴリー3 | 国立大学法人 東京科学大学 |
| カテゴリー4 | 国立大学法人 山梨大学 |
準グランプリ
| カテゴリー1(東地区) | 金沢大学人間社会学域 学校教育学類附属高等学校 |
|---|---|
| カテゴリー1(西地区) | 島根県立益田高等学校 |
| カテゴリー2 | 一般社団法人Girls Unlimited Program |
| カテゴリー4 | 公立大学法人 埼玉県立大学 |
三菱みらい育成財団賞
| カテゴリー5 | 認定特定非営利活動法人カタリバ |
|---|
受賞結果

カテゴリー1(東地区)群馬県立伊勢崎高等学校
iTanQ~伊高の
探究が世界をつなぐ~
【選考委員からのコメント】
全生徒が参加する総合的な探究の時間iTanQ蒼穹に加え、4つの有志探究活動が効果的に配列されていることで、学校を越えた活動を積極的に後押しするプログラムになっています。また、外部連携やフィールドワーク支援などプログラム目標を達成するための仕組みが講じられている点を含めグランプリに相応しいと評価しました。最後に、成果発表動画についても、生徒の意欲だけでなく、学校の熱意も伝わる素晴らしい動画であったことも申し添えます。
カテゴリー1(西地区)京都市立京都奏和高等学校
Make smile
―心のエンジンをかける
ための鍵となる「笑顔」の見つけ方―
【選考委員からのコメント】
不登校経験など困りを抱える生徒の理解を基盤に、生き方(働き方)を追究する「キャリア」と生徒の活動(アクション)を促す「ビジテック」の二本柱で段階的に取組みを進め、生徒の変容を着実に促しています。地域行政・民間企業・教員志望の大学生など独自の視点でさまざまな連携も進み、地域活動へ広がっています。
困りを抱える生徒が取り組む探究活動のモデルケースとして全国に発信できる実践として高く評価しました。
カテゴリー2株式会社 トモノカイ
自由すぎる研究EXPOと連動した、
国際映画祭接続型、
映像ドキュメンタリー制作
プログラム
【選考委員からのコメント】
札幌国際短編映画祭においては、このプログラムのためU18部門が新設されました。同部門へのエントリーを目標に、高校生が3分半の短編映画制作に取り組みました。同社が主催する「自由すぎる探究EXPO」応募者3,857件のうち490件の入賞者に映像制作カリキュラムを実施し、実際に20件が映画祭にエントリーし、5件の入賞に繋がりました。
短編映画製作を通じた探究活動による高校生の成長と、自走に向けた同社の協賛獲得活動を評価しました。
カテゴリー3国立大学法人 東京科学大学
女子STEAM生徒の
未来チャレンジ
「みらいの扉キャンプ・
みらいの扉ビジット」
【選考委員からのコメント】
理工系分野の女性技術者・研究者を増やすことが課題である中、東京科学大学、お茶の水女子大学、奈良女子大学の3大学が協働して、全国から推薦・選抜された女子高校生に2泊3日の合宿を提供し、研究室訪問なども組み合わせています。先進的で多彩な内容の講義や実験・実習の充実度とともに、グループワークも通じて地方で理系進学を目指す女子高校生に横の繋がりも提供できており、意義とインパクトの大きなプログラムとなっています。
カテゴリー4国立大学法人 山梨大学
実践! 風林火山:
VUCA時代に生きる学生の
ための教養教育「シン・ナシダイ」
【選考委員からのコメント】
全学共通教育を全面刷新し、6つの科目群に再編するとともに、その一つであり改革の目玉となる、ワークショップ科目「創発PBL科目群」を創設した取組みです。助成初年度にトライアル授業と教員研修を実施したうえで、全学部の1年生全員を対象に、共通の内容で設計された授業を行っています。学生も担当教員も、それぞれ学部を跨って小教室に分かれて混じり合い、多様性を活かした創発的な学びづくりが行われており、高い継続性も期待できます。

カテゴリー1(東地区)金沢大学人間社会学域
学校教育学類 附属高等学校
ミライシコウする
グローバル人材の育成
~地域と世界に開かれた
北陸コンソーシアムの
探究マインド醸成を目指して~
【選考委員からのコメント】
5つのアライアンスを活用して、単なる横展開にとどまらず多角的な活動展開に取り組まれています。特に北陸圏域内高校とのコンソーシアムは地域全体の探究学習のレベルアップの観点からも大いに期待されます。同校は、探究の第2段階と言える質の高い取組みを行われていますが、大学附属校というアドバンテージを除いても高いレベルで他校の模範となる取組みであると評価しました。

カテゴリー1(西地区)島根県立益田高等学校
益田圏域での理数教育を
発展させるための小学校・
中学校・高等学校連携プログラム
【選考委員からのコメント】
同校は、SSHの経験を活かし、小中連携よる理科教育の推進に取り組んでいます。特に「益田さいえんすタウン」では、小中学生の指導者を務めリーダーシップを発揮することにより、生徒は地域の発展に繋がる意欲や主体性を育んでいます。高校の使命を生徒もしっかりと理解して取り組まれている点も評価しました。地域行政とも連携して引き続き地域活性化と理科教育の推進に取り組んでいただくことを期待しています。

カテゴリー2一般社団法人Girls Unlimited Program
Girls Unlimited Program:
体験格差を解消する
エンパワメントプログラム
【選考委員からのコメント】
以前から米国大使館の支援を受けて女子高校生向けにさまざまなロールモデルを提示してきたプログラムです。これまで東京・大阪で実施していましたが、財団の助成を受けたことで、地方都市に展開を目指し、独自のネットワーク開拓と財団の繋がりも活用し、初年度は名古屋、札幌で開催に至りました。
スタンフォード大学の「ライフデザインメソッド」に基づく、メンターとの対話を深め、自身の人生とキャリアを見つめ直すワークショップの手法も評価しました。

カテゴリー4公立大学法人 埼玉県立大学
多層的・分野横断的な批判的
対話実践プログラム
-教員・SA・
学生の協働で知を織り上げる-
【選考委員からのコメント】
100人規模の学科混成の受講学生を対象に、専門分野の異なる複数の教員が、各々のバックグラウンドを活かした批判的対話の例を見せ、それを踏まえて学生間での対話を行うプログラムです。全学科共通で2年次以上が受講する発展階層科目として提供されています。大人数の教室で対話を進めるうえでの困難に対して、種々の人的・物的な資源制約の中でも工夫を重ねつつ、科目の増設により1学年約400人全員への提供を目指すなど、発展を続けています。


カテゴリー5認定特定非営利
活動法人カタリバ
高校生に意欲と創造性を届ける
ための「伴走力向上」と
「校内推進体制づくり」を
目指した伴走型研修
【選考委員からのコメント】
高校毎に管理職を含めた3名程度の教員が参加し、半年間にわたって3回の集合研修でグループワークを行い、探究学習の伴走手法を学び、各校での「探究チーム」の組成に繋げるプログラムです。
同団体がこれまで培ってきた探究での伴走手法を伝えるとともに、各校管理職も参加し、担当教員だけの取組みにしないことで、各校に持ち帰って実施する際に実効性が高い点が評価されました。

パネルディスカッション・
振り返りワークショップ
「探究的な学びの充実に向けて~つながる・深める・拡げる~」をテーマに、助成先4団体によるパネルディスカッションが実施されました。パネリストには、大阪府立淀商業高等学校 秋月麻衣氏、特定非営利活動法人しずおか共育ネット 井上美千子氏、北海道札幌西高等学校 相馬利幸氏 、兵庫県立御影高等学校 橋本淳史氏が登壇し、学校間連携による持続可能な仕組みづくりや地域全体を巻き込む探究文化の醸成、同窓生ネットワークの活用、校外体験を通じた学びの深化など、特色あるアプローチが紹介されました。また、失敗を許容する環境の重要性や教員の役割の変化といった共通課題も浮かび上がりました。
モデレーターの塩瀬隆之氏(京都大学総合博物館准教授)は、「以前は探究担当教員が孤軍奮闘する状況が目立ったが、今回のお話を伺い、組織的な協働へと移行し、活動が次のステップへと深化していることを実感した」と総括しました。

助成先の皆さまをパネリストに迎え、特色ある実践や課題について議論が行われました

パネルディスカッション中は、参加者が真剣に耳を傾け、各取組みに関心を寄せていました

当日は全国各地から132名の方にお集まりいただきました
続いて行われた「振り返りワークショップ」では、参加者全員が3~4人のグループに分かれ、簡単な自己紹介を行った後、「ここまでの話を聴いて感じたこと、考えたこと」について意見を交わしました。グループ替えを2回行い、異なる立場や背景を持つ参加者同士が交流し、視点を広げる機会となりました。
最後には今日の振り返りを踏まえた「オープンマイク」が行われ、探究学習における生成AIの活用や教員の働き方改革、多様な背景を持つ生徒一人ひとりへの向き合い方など、教育現場が直面する重要な課題について具体的な悩みや実践例が共有されました。「同様の課題を抱えている」「その取組みを詳しく知りたい」といった声が相次ぎ、積極的な意見交換が行われました。
閉会の挨拶を当財団の妹背正雄 常務理事からさせていただいた後は、ホワイエにご移動いただき、懇親会でさらに交流を深めていただきました。

「振り返りワークショップ」では、少人数のグループで感想や意見を共有し、活発な議論が行われました

オープンマイクでは、参加者が挙手して自身の課題や実践例を会場に向けて発信し、教育現場の課題解決に向けた新たな視点が共有されました

妹背常務理事から閉会のご挨拶をさせていただきました

アワード終了後には懇親会が開催され、参加者同士がリラックスした雰囲気の中でさらに交流を深めました
 参加された皆さまのご感想
参加された皆さまのご感想
- 皆さんの何かの参考になればと思って、本校の取組みを発表させていただいたところ、実際いろいろな方が声をかけてくださいました。子どもたちの「困り」は、皆さんどこかで絶対に出合っているはずで、今日の私の話がそれに気づくきっかけとなったのであれば、本当にありがたい機会を頂いたと感じています。今日出会った学校との交流も決まるなど、今後の進展が楽しみです。(カテゴリー1)
- 例えば発表会なども生徒たちが自ら企画して運営していくなどのお話を聞いて、『好きなことを調べる』という探究のその先のステージがあって、今までとは違う資質能力の育成につながるのではないかという発見がありました。また地域の学校やオンラインを通していろいろな学校の子どもたち、同世代だけじゃなく異世代、地域の大人が関わることでお互いを高め合うこともできるようになるとも感じました。皆さんの話を伺って、次にこういうことをしようというメモをたくさん持って帰ることができました。(カテゴリー1)
- いろいろな先生方にお会いできて、ここでしか聞けないお話も伺うことができて、仲間がいるんだという実感を持つことができました。ネットワークを作るうえで、三菱みらい育成財団の助成先であれば、お互い安心であり、貢献したいという気持ちが生まれます。今日は非常にありがたい機会を頂いたと思っています。(カテゴリー2)
- 普段は大学に勤めているので、高校の先生や民間企業の方と接する機会が非常に限られているのですが、今日はいろいろな立場の方から高校生や大学生の教育についてどう考えているのかという話を聞かせていただきました。また高校でも膨大な労力と時間をかけて探究型学習に取り組んでいることも印象的でした。我々も自分で問いを発見して解決していくような教育を展開しているのですが、大学生は「高校と同じことをやっているんじゃないか」と思っているのではとも感じました。そのような意味では、高大連携の中で子どもたちが探究学習を通して成長できる環境をつくっていければと感じました。(カテゴリー4)
- 探究に関わる問題が一回りして、もっと大きなフレームとして考えていかなければならないフェーズに来ていると、皆さんのお話をお伺いして感じました。私たちは今ちょうど小・中学校の探究活動にも関わろうとしているのですが、小学校から大学まで一体的に探究に取り組む仕組みも大事になってくるんじゃないかなと思っています。今日は確実に探究の歩みが進んでいるというポジティブな感想と、次のフェーズに向けて”闘い方“を変えていかなければいけないという感想を持ちました。(カテゴリー5)



