Program(1)Touch the Future高校生向け医療体験学習
(2)DoctorX! ハイブリッド・ミーティング
(1)医師になりたい高校生が地域医療の拠点病院や大学病院に5日間密着する次世代支援企画。「命を預かる覚悟はあるか」「どのような医師になりたいのか」などをリアルな医療現場で体験しながら考えることを目指す。2024年夏は7病院が生徒30人を受け入れ、6病院では医学生が生徒たちをサポートする。この体験の集大成として5名程度の生徒が12月、日本地域医療学会で発表する予定。
(2)トップドクターが講義するハイブリッドMTGで、会場の中高生と遠隔地から参加する生徒をオンラインでつなぎ、リアルタイムでやりとりをする。第1回目の講師は加藤友朗・コロンビア大学外科学教授。医療体験の一環という位置付けで、MTGに参加した生徒の一定数が(1)に応募をしている。大都市圏以外でも実施して、広く生徒たちが参加できることを目指す。



活動レポートReport
未来の医療人の「志」を育むため、医学部志望の生徒に医療現場を体験してほしい
「学業成績が優秀というだけで医師を目指すのではなく、世の中に貢献したいと志す若者にこそ、医療の担い手になってもらいたい」―こうした理念のもと、真剣に医療に携わりたい高校生たちに医療現場の“リアル”を体験してもらう機会を提供するNPO法人Touch the Future。その活動の原点は、発起人として理事長を務める土井毅氏が大手新聞社の教育支援部門に在籍し、高校生を対象とした医療現場体験プロジェクトを企画・運営していたことに遡る。
「医療現場では、患者さんの苦しみに寄り添うことが求められ、命の終わりに向き合うことも少なくありません。核家族化の影響もあって病や死と直面する機会が乏しくなっている子供たちにとっては想像外のことも多く、初めて人の死に触れて大きなショックを受けることも少なくありません。人の死に限らず、医療の現実とのギャップからくるミスマッチは、臨床教育の場でも大きな課題になっています。そこで、早い時期に医療現場を体験し、患者さんの命を預かる覚悟を自身に問いかけてもらうべく、想いを同じくする医療関係者の支援を得てプロジェクトを開始しました」と土井氏は振り返る。
約5年にわたり約120名の高校生に体験の場を提供する中で、「医療ドラマなどでは描かれない現実の厳しさを体感できた」「身を粉にして働く医療関係者の皆さんの姿に圧倒され、自分にそれだけの覚悟があるのか葛藤を覚えた」といった声が得られ、確かな手ごたえを得るとともに、プロジェクトの社会的意義を確信したという。
その後、新型コロナウィルス感染症の拡大によりプロジェクトが中断されたことを機に、教室では得られない学びを得る場を維持・拡大しようと早期退職を決意。それまでの活動で知己を得た医療・教育関係者とともに、2022年に同法人を立ち上げた。「当法人の役員には、地域医療を担う病院や大学病院で高度先端医療をリードする先生方が名を連ねています。医療や大学教育の最前線で多忙な日々を送りながらも、自身の現場に高校生を受け入れ、他の医療関係者にも働きかけていただく先生方には、感謝の言葉もありません。私たちに共通するのは、“志ある若者に医療に携わってほしい”という強い願いであり、それこそが活動の原動力になっています」と土井氏は語る。

1989年に大手新聞社に入社し、地方支局などを経て教育支援に携わり、産官学の協力を得て多くの教育イベントを手がけてきた土井氏。「医療と教育は社会の重要なインフラであり、その未来を支える若者たちをサポートすることが私たち大人の責任」と、この事業に関わる強い使命感を語った。

法人名であえて「医療」に触れなかった理由について、「当法人のミッションは、あくまで未来の担い手を育むことであり、そのフィールドは医療だけにとどまらないため」と土井氏は説明する。実際、プログラムへの参加を機に自身の将来について考え、医療機器開発や地域振興、海外支援など医師以外の進路を選ぶケースも少なくないという。
体験学習とハイブリッド・ミーティングの両軸で、中高生に医療現場のリアルを届ける
2022年度に2つの病院での医療体験学習からスタートしたTouch the Futureの活動は、2年目からは中高生を対象にトップドクターが講義するハイブリッド・ミーティングが加わり、以降は二本柱での活動を展開している。
「ハイブリッド・ミーティングは、『地方の生徒にも医療現場を知る機会を設けてほしい』という、九州や東北など地域の進学校の要望をもとに始めたものです。講演を実施するリアル会場とオンライン参加のハイブリッド形式にすることで、遠隔地からの参加を容易にするとともに、体験学習に参加できない中学生にも対象を広げています。
内容面では、一方的に講演を聞くだけでなく、オンライン参加の生徒も含めたグループディスカッションも行うなど双方向性を重視しています。こちらも医療体験の一環と位置づけており、参加後に体験学習に応募する生徒が増えています」と土井氏は企画意図を語る。
一方の医療体験学習は、「先進医療体験」と「地域医療体験」の2種類のメニューが用意されており、近年は後者に注力しているという。「都市部で暮らす高校生にとって、過疎地や離島などにおける医療の実態は想像を絶するものがあります。参加者たちは地域病院での体験を通じて、一人何役をもこなさざるを得ない医師の奮闘ぶりを目の当たりにするとともに、その背景にある医師不足・医師偏在や人口減少の深刻化といった地域課題について、主体的に考え始めるようになります」。
土井氏が語る体験の意義を深めるべく、地域医療体験の参加者は院内の医療体験が始まる2日前に現地入りし、一日がかりのフィールドワークに臨む。「地域の方々との対話・交流を通じて、参加者は産業やインフラの担い手不足など課題の深刻さを体感すると同時に、地域ならではの暮らしの豊かさにも触れることができます。そうした経験を早期に持ってもらうことで、将来、地域を思いやれる医療人が増加することを期待しています」(土井氏)。
フィールドワークを終えた参加者は、メンター役を務める医学生とともに、病院宿舎や借上げ施設などで寝食を共にしながら5日間の医療現場体験に臨む。そこでは、参加者それぞれが入院患者を受け持ち「患者さんの望みを探り、どうしたら幸せになってもらえるか」とミッションが課されるという。「世代が異なる上に、病に苦しむ患者さんとコミュニケーションは容易ではありません。何とか会話してもらおう、心を開いてもらおうと試行錯誤するなかで、『寄り添う』という行為の本質を体感できるのです。そうした経験を積むことで、医師がやりたい医療ではなく、患者が望む医療を行うことの意義や意味を考えてもらえればと思っています」と土井氏はプロジェクトの意義を語る。

高校生に入院患者を担当させるという取組みは、患者さん本人やご家族の協力なしには成り立たない。受入先の医療機関では、事前に本人・ご家族に医療体験学習の内容や意義を説明し、理解と承諾を得た上で実施。どう接することが患者さんのためになるか、試行錯誤する中で得られる気づきは、参加者にとって忘れられない財産となっている。
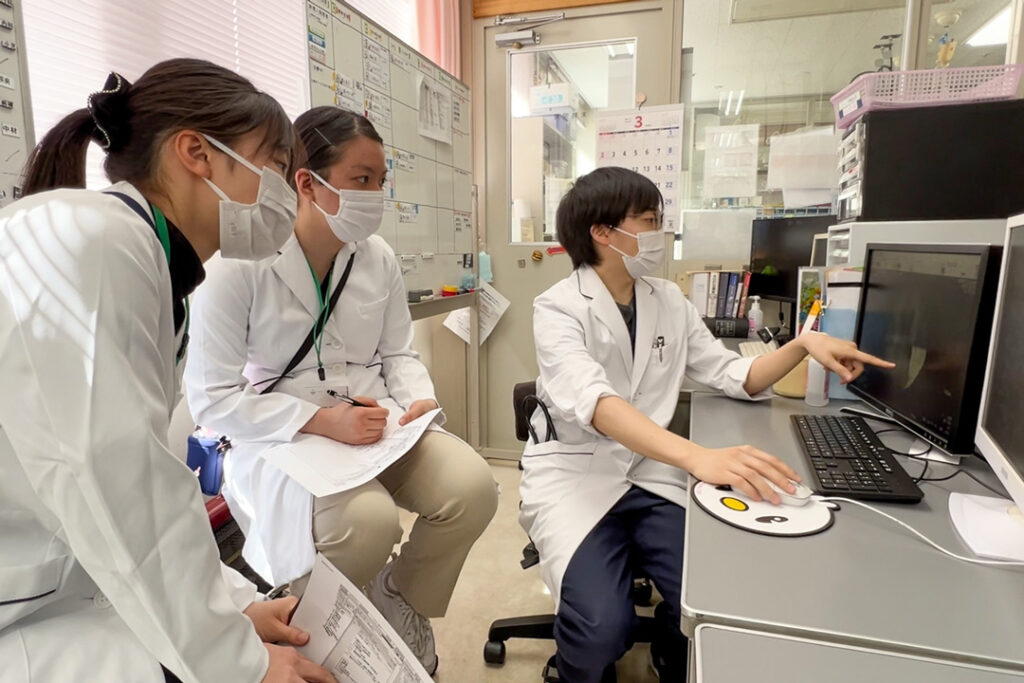
医療現場での体験を通じて、医療とは医師だけでなく看護師や介護士、ソーシャルワーカーなど多様な医療従事者の組織的な連携によって成り立つものだと体感。チーム医療の大切さを知るとともに、選択肢の多様さを知り、自身の将来について考えを深めるきっかけとなっている。

地域医療体験の参加者は、約1カ月の事前オンライン学習を経て、地域フィールドワークに臨む。地域の実態を知り、課題を理解することで、医療従事者にできることを考える機会になるという。「地域住民に医療に対する満足度をインタビューし、そこで得られた声を病棟で生かすなど、フィールドワークでの学びを医療体験につなげられる生徒が増えています」(土井氏)。

医療体験学習で得られた学びを言語化するための場として、日本地域医療学会で発表の機会を設けている。2025年10月に開催された同学会の学術集会では、代表者4名が発表。「医師の不足や過重労働が課題となる中で、どこまで患者さんに寄り添えるのか」など医療現場で抱いた疑問について、その後のトーク・ディスカッションも含めて活発な意見交換が行われた。
医学生メンターの献身的なサポートが、次世代のメンターを生む好循環に期待
2024年度は、医療体験学習を7~8月に7病院、年明けの2~4月に3病院で実施し、計41名が参加。ハイブリッド・ミーティングは11月に東京、3月に愛媛で開催し、どちらも80~90名が参加した。各病院で受け入れる生徒数は3~4名が限度であり、応募者は小論文とオンライン面接の2段階で選考される。参加者や教諭の口コミによる認知拡大を背景に、年々、応募者が増えており、いかに体験学習の受入先を拡大するかが当面の課題だという。
「選考時に小論文を読んでいると、どの応募者も医療に対する真摯な想いを抱えていることが伝わってきて、できれば全員を参加させたいと思うほど。一人でも多くの応募者を受け入れられるような環境を整備することが私たちの使命だと思っています。幸いなことに、学界での発表を聞いて『当院でも受け入れたい』と手を挙げていただける病院もあり、2025年度は北海道の利尻島でも地域医療体験を実現できました。今後も当法人の役員陣はもちろん、各地の医療関係者と築きつつあるネットワークを駆使して、協力いただける病院を増やしていきたいと思っています」と語る土井氏だが、参加者の拡大を実現するには、受入先の病院だけでなく、参加者を支える医学生メンターの拡充も不可欠だという。
「医学生メンターは、単なる助言・指導役というだけでなく、医療現場での現実に戸惑う参加者の心のケアも担うなど、プロジェクトに欠かせない存在です。特に地域医療体験では、事前学習や前日のフィールドワーク、さらには体験後の学会発表も含め、長期にわたって献身的なサポートを行います。自身の学習・研修で大変な中でも、熱意と課題意識を持って参画してくれている医学生の負担を減らすためにも、メンターの拡充は必須と考えています。ありがたいことに、最近では地域医療にコミットする医学生の任意団体の協力もあり、手を挙げてくれる医学生が増えつつあります。加えて、医療体験学習に参加した経験を持つ医学生が『今度は自分たちが高校生を支える番』と協力してくれるのも嬉しい限りです」と土井氏は語る。
「この法人を立ち上げた際、現役員の医療関係者から『10年間の壮大な社会実験のつもりでやってみよう』と言われました。しかし、これまでの活動で痛感しているのは、10年で終わらせることなく、次の世代にも受け継いでいかなければということ。早くから医療の現場を知り、患者さんや地域を思いやる原体験を持った医療人が増えることが、これからの豊かな社会づくりに貢献するはずです。この信念を忘れずに、マネタイズ面も含めて持続可能なプロジェクトにしていきたい」と、土井氏は事業の将来に向けた決意を語った。

本人の意思確認も難しい患者の延命治療の判断など、答えの出ない問いに直面した際には「自分の戸惑いを言語化することが大切」だと土井氏は語る。一日の振り返りなどで、医学生メンターと語り合う時間は、患者さんの命に寄り添う覚悟を養うための重要な役割を果たしているという。

プログラムの告知は賛助会員校や教諭らに案内して校内掲示をお願いしているという。最近目立つのは、案内していない学校の生徒からの応募だという。「医師になりたい生徒の間に、現場を知りたいという意識が広がっているのでは」と土井氏は分析する。

