Program探究が平戸・日本の未来へつなぐ
~猶興精神(自立・自発)を心のエンジンに~
高校生が主体的に取り組む探究活動を通じて課題発見力、課題解決力を育み、「変化」をもたらす発信力をもって地域や社会全体に貢献できる人材を育成する。
普通科では、「地域」に視点を置いた「ふるさと平戸未来探究」を実施する。
自分の興味・関心をもとにチームをつくり、平戸市及び北松地区が抱える地域課題に着目し、地域の持続可能な発展につながる課題解決策を立案・実践し、検証する。
文理探究科では、「自己」と「社会事象」に視点を置いた「生き方探究」を実施する。
1年次では、自身の価値観を徹底分析する「Egoゼミ」、日本や世界が抱える様々な課題について知見を広げる「Societyゼミ」に取り組み、自己理解と社会理解を深める。2年次以降は、外部機関と連携を図りながら、より専門的な分野に焦点化した課題探究活動に取り組む。
「猶興精神(自立・自発)を心のエンジンに」をスローガンに、“生徒が自走する探究活動”を推進する。
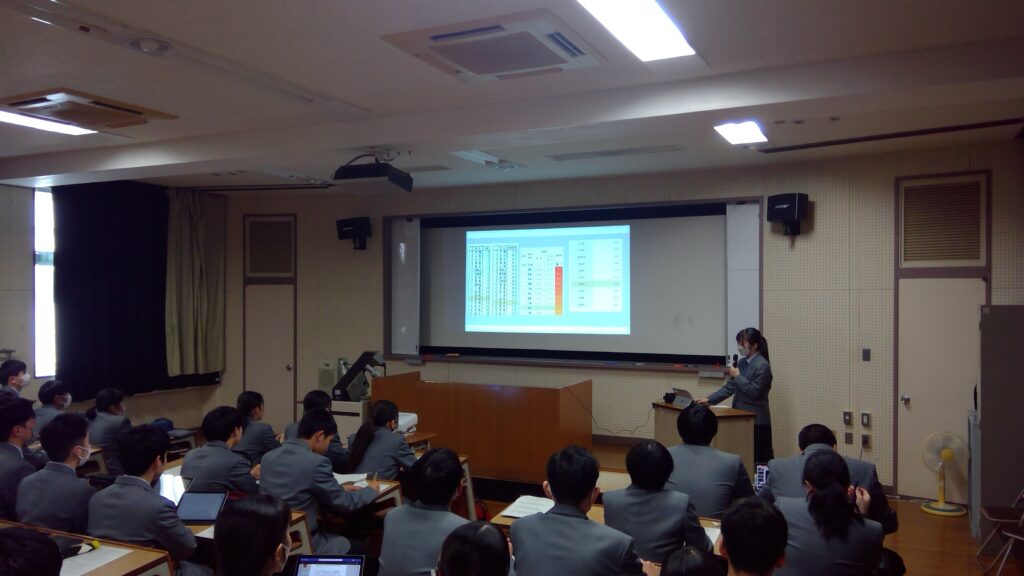


活動レポートReport
先生も学び、生徒も成長する学校づくり
長崎県平戸市に位置する猶興館高校は、普通科と文理探究科を擁しており、普通科1年生では自分の「好き」を深掘りしていく「ミニ探究」で探究の基礎力を付け、2年生では地域課題解決型の探究学習「ふるさと平戸未来探究」を展開している。2019年度から始まったこの活動の成果について、同校の坂本豊樹教頭は「当初は学校が講演をお願いした市役所を起点に大人とつながる生徒が多かったのですが、最近では生徒と一緒に課題を考え、取り組んでくれる地域の方々を自ら見つけ出し、つながる事例が増えてきています」と話す。また平戸の名所でダンスをする動画をSNSで発信したところ、海外のアーティストから反響があり、それをきっかけに英語をもっと学びたいと大学進学を決めた生徒も出るなど、探究がきっかけとなって今まで見えなかった将来の可能性を見いだす事例も出てきた。
一方、2023年度から新設された文理探究科では、1年生を対象に、自身の価値観や興味を徹底的に分析する「Egoゼミ」と社会課題について学びを深める「Societyゼミ」を実施。「探究の基礎は、自分を知ること、そして社会を広く見る目を養うこと。これらを1年生の段階でしっかりと学ぶことで、2年生以降の探究活動がより深まります」(坂本教頭)。近年は学科の名前が示す「文理融合」も進んでおり、「機能性を表示したおにぎり宇宙食に、ご当地的な付加価値をつけて、商業ベースに乗せる」といったアプローチをしたグループも見られるようになった。
生徒たちの探究活動が年々ブラッシュアップされている要因の一つとして、坂本教頭は研修部の存在を挙げる。「私が本校に赴任した2021年度に、教務部に所属していた研修部が独立し、1~3学年の担当3人の教員が主体となって、教員向けの研修を強化しました。1年目は生徒たちに身に付けてもらいたい力、2年目は伴走、3年目は生徒の主体性をテーマに研修を行いました。教員の一体感が深まると同時に、生徒たちに見えるように研修の成果を職員室の廊下側に貼りだしたことで、『自分たちと同じように、先生も大人も学んでいる』と生徒たちのモチベーションアップにつなげてもらえたのではないかと思っています」(坂本教頭)。
「生徒が自走する探究活動」を掲げる同校の取組は、生徒が自走するためには、先生方の伴走力のアップが不可欠であるという、気づきを与えてくれる。

探究活動専用の教室の整備も進められており、2025年度から本格的に活用される予定だ。この教室は、情報共有やディスカッションの場としてだけでなく、専門機関とのオンライン会議の拠点としても活用される計画だ。

